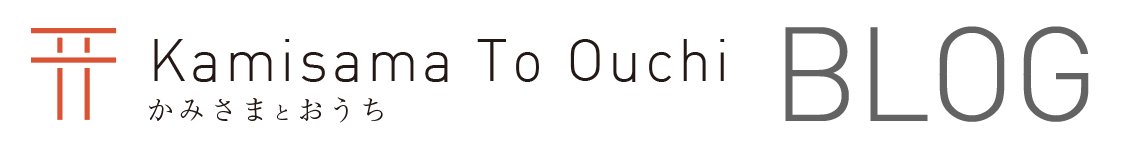【盛り塩のやり方と意味】清めの習慣に、新しい選択肢を。
玄関に、そっと置かれた小さな白い塩の山。
「盛り塩って、なんのためにするの?」
「どうやって置くのが正しいの?」
そんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
この記事では、盛り塩のやり方・意味・歴史について分かりやすく解説しつつ、
現代の暮らしに合った、新しい「飾る盛り塩」のかたちもご紹介します。

■ 盛り塩とは?その意味と始まり
盛り塩とは、塩の持つ清めの力を活かし、場を整える日本の習慣です。
その由来は古く、
- 神道における「清め」の象徴としての塩
- 古代中国の陰陽五行思想
- 平安時代の貴族文化
- 江戸時代の商家での「客寄せ」のまじない
などが混ざり合いながら、現代に受け継がれてきました。
特に、玄関・トイレ・台所などに塩を置くことで、
邪気を遠ざけ、気を整えるとされています。

■ 盛り塩の正しいやり方
盛り塩はシンプルですが、いくつかの基本があります。
▷ 用意するもの
- 清潔な白い塩(天然塩がベスト)
- 受け皿(陶器製やガラス製など)
- 型を使って三角錐に盛ると見た目も美しく
▷ 置く場所
- 玄関の左右
- トイレ・キッチン・リビングの四隅
- 店舗ではレジ前や入り口付近に置くことも
▷ 頻度と交換時期
一般的には1週間に1回程度交換が理想とされます。
ただし、梅雨時期や気になるタイミングでは早めの交換も。

■ でも実際…盛り塩、こんな悩みありませんか?
・すぐ湿気って形が崩れる
・交換のたびに手間がかかる
・見た目が雑になってしまう
・塩がこぼれて掃除が大変
・置き忘れて逆に気になる…
そう、**伝統的な盛り塩には“手間のかかる儀式感”**があり、
日常の中で続けるのが難しくなっている人も少なくありません。

■ 新しい選択肢。「飾る盛り塩」というアイデア
そこでおすすめしたいのが、
**飾って楽しめる“モダンな盛り塩”**です。
清らかな海の恵み、日本産の塩を飾る。
「かみさまとおうち」では、
日本の海で生まれた清らかな塩と、きらめく大粒の岩塩を、
透明な樹脂の中に封じ込めた、新しいスタイルの盛り塩をつくりました。
- 形が崩れない
- 汚れない
- 交換いらず
- 光を受けて美しく輝く
- 玄関や棚に置くだけで“清めの空間”に
まさに、「祈り」と「インテリア」を融合させた現代の盛り塩です。
■ おすすめの飾り方
- 玄関の棚:光が当たる場所で特に美しく
- 寝室や書斎:集中したい空間に
- トイレや水まわり:清めの意識を保つために
- ギフトにも最適:縁起物としても人気です


■ まとめ:毎日の中に“整える力”を
盛り塩は、単なるおまじないではなく、
「自分と向き合い、空間を整える」ための日本の知恵です。
でも忙しい現代では、
無理なく続けられる形も大切。
だからこそ、
見た目も美しく、手間もいらず、気持ちが整う——
そんな「飾る盛り塩」が、新しい祈りの形になるかもしれません。